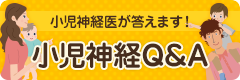第55回小児神経学セミナーイントロダクション
イントロダクション (講師敬称略、講演順)
随時更新して参りますのでお楽しみに!
不登校:小児科医だからこそできる教育医療連携
加藤 善一郎(岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科)
不登校はこの30年で中学生5倍以上小学生10倍以上と増加し続け35万人となっています。多くのお子さん・家族と共に歩み、教育現場と協力してきたことで、小児科医としてできること(内的要因・外的要因の診断、治療対応、教育医療連携)がわかってきました。医師を頼ってこられたとき、どう判断し対応すべきかについて概説します。
原初の道徳心萌芽を構成論的に解明するための内臓付赤ちゃんモデル構築
國吉 康夫(東京大学大学院情報学環・学際情報学府先端表現情報学)
道徳心が人間の発達過程の中でいつどのように発生するかを解明できれば、将来のAIの深い根源的な部分に道徳を実装できるかもしれない。我々はこれまで、人間の初期発達の構成論的モデル化のために、精密な身体と脳神経系および子宮内環境や新生児環境を含む発達シミュレーションを構築して来た。これに内臓モデルを構築、統合することで、原初の情動、美感の萌芽を再構成し、それが道徳心の萌芽につながるのではないかとの予測のもとに研究を推進している。
小児全身性エリテマトーデス(SLE)診療のup-to-date
~「小児期発症全身性エリテマトーデス診療 ガイドライン2025」の内容から~
森 雅亮(東京科学大学新産業創生研究院生涯免疫医療実装講座/聖マリアンナ医科大学 リウマチ・膠原病・アレルギー内科)
全身性エリテマトーデス(SLE)は、皮膚や関節、腎臓など多臓器に影響を及ぼす自己免疫性炎症疾患であり、特に小児期に発症するケースは病勢が強く、重篤な合併症を引き起こすことが多い。日本リウマチ学会や小児科関連分科会によって「小児期発症全身性エリテマトーデス診療ガイドライン2025」が作成された。本セミナーでは中枢神経ループスを中心にガイドラインの内容を紹介・概説する。
小児脳MRIの勘所:画像所見から病態を診る
髙梨 潤一(東京女子医科大学八千代医療センター小児科)
臨床経過・神経診察に加えて画像読影に精通することは小児神経科医にとって大きな武器となりえます。しかしながらMRI技術は日進月歩であり、内容を理解し臨床に応用することは容易ではありません。基本となるT1, T2, FALIR画像に拡散強調像、Arterial spin labeling (ASL) 法、MR spectroscopy (MRS) を加えることで、病態に迫ることが時に可能となります。MRIを診ることが楽しくなるようなエッセンスをお伝えしたく存じます。
限局性学習症の診断と支援-発達性ディスレクシアを中心に―
関 あゆみ(北海道大学大学院教育学研究院)
限局性学習症とは読字、書字表出、算数における持続的な困難であり、知的能力やその他の障害、言語能力、環境等では説明できないものを指す。DSM-5やICD-11の診断基準は文部科学省の定義とはやや異なることから、学びの場の選択においては注意が必要となる。また、DSM-5の診断基準には、欧米での教育における支援方略の変化が反映されている。本講義では支援との関係から限局性学習症の診断について概説する。
定位的頭蓋内脳波(SEEG)を用いたてんかん原生領域の診断
クー ウイミン (大阪大学医学系研究科脳神経外科学)
てんかん外科治療によって良好な発作予後を得るためにはてんかん原生領域の診断を的確に同定することが重要である。発作症状、脳波から各種画像検査まで非侵襲的に得られた情報よりてんかん原生領域は推定されるが、その局在が十分に明確でない場合、切除範囲を評価する必要がある場合や機能領野との境界を確認する必要がある場合には焦点切除する前に頭蓋内脳波による精査というステップを経る必要がある。頭蓋内脳波は従来開頭を要する硬膜下電極の留置で記録されてきたが、近年開頭を要さず定位的に留置される電極で記録するより低侵襲な方法(SEEG)が普及し、小児の領域でも行われるようになってきた。本講演ではSEEGを用いたてんかん原生領域の診断について、小児例における留意点を適宜取り上げながら、適応、プランニング、判読と解釈を中心にまとめる。
ランチョンセミナー
小児のCritical Care EEG
福山 哲広(信州大学医学部小児医学教室新生児・療育学講座)
ICUや救急現場での急性期脳波(Critical Care EEG:CCEEG)の主目的は、意識障害患者における非けいれん性てんかん重積の診断である。小児科領域ではNICU・PICUで積極的に活用され、正確な病態把握と治療方針決定に寄与している一方、二次救急病院での普及が課題である。本講演では実症例を用いてCCEEGの基本的な判読と運用上の課題を解説する。
モーニングセミナー
小児神経疾患における遺伝子治療の今とこれから
小島 華林(自治医科大学小児科)
小児神経疾患は単一遺伝子異常で発症する疾患が多く、遺伝子治療が期待される分野である。現に、SMA,DMD,AADC欠損症に対する遺伝子治療は承認され臨床応用されている。今後も適応拡大が予想される遺伝子治療の基礎知識、現在の開発状況をシェアし、今後の展望について一緒に考えましょう!今は治療法がない疾患も、治療法が見つかるかもしれません。
Group discussion
G1− 神経伝導検査・針筋電図検査の結果の解釈について考える
石山 昭彦(東京都立神経病院神経小児科)
神経伝導検査や針筋電図の所見は、何を意味しているのか? 単に神経原性変化、筋原性変化という「検査結果を診る」のではなく、その「検査所見が意味するところは何か」と “所見を解釈” することを意識すると、病態理解や診療における応用力が格段に上がります.
筋疾患、末梢神経疾患などの具体例から、それらが筋病理やMRI所見にどのように関連し、病態や診断へと結び付くのか、電気生理学的検査の所見の解釈について一緒に学びましょう.
G2−遺伝学的検査解釈実習
吉田 健司(京都大学医学部附属病院小児科)
小児神経領域では遺伝子異常に伴う疾患が多く、近年は保険で実施できる遺伝学的検査も増えています。ただし、遺伝子変化が見つかっても必ずしも病的とは限らないため、正しい評価が非常に重要です。本実習では、シークエンスで同定されたバリアントについて、インターネット上のデータベースや病原性評価ツールを用い、各自のPCで実際に解析を行います。遺伝学的検査の解釈を実践的かつ体系的に学ぶことができます。
G3− 倫理
岡崎 伸(大阪市立総合医療センター小児神経内科)
小児神経医が対象とする疾患や病態は数千種類とされているが、その診療においては多くの倫理的ジレンマを経験する。
例えば、保険適応外(保険適応外年齢も含む)薬剤の使用、侵襲が強い治療の施行などに始まり、重篤な状態における家族の希望内容や子どもの最善の利益を考えるときの判断などにも及ぶ。本GWでは、仮想症例をもとに、倫理的ジレンマを検討する時に必要なことや検討の方法などを一緒に考える機会としたい。
G4− EEG
丸山 慎介(鹿児島大学病院小児科)
EEG(脳波)検査を理解し活用していくことは小児神経科医にとって重要です。このGroup discussionでは、初学者向けに脳波ビューワーの使い方、脳波の判読の仕方、所見の記載方法などをとり上げます。Windows PCをお持ちの方は持参いただき、実際の脳波データを扱って学んでいただければ、と思います。脳波の所見をカルテにどう記載すればよいか、どうやって脳波の勉強をすればいいのか、と悩んでいる先生の手がかりになれば幸いです。
Clinical Conference
伊藤 祐史(名古屋大学医学部附属病院小児科)
Clinical Conference では、私たちが診断や治療に苦慮した症例を提示いたします。聴衆の皆様には、その診療過程を疑似体験していただきながら、診療のポイントについて活発に議論していただければと考えております。さらに、Conference の最後には本症例の理解を深めるための Special Lecture もご用意しております。皆さまの日々の診療に少しでもお役立ていただければ幸いです。
Special Lecture
成田 綾(医誠会国際総合病院小児科)
特別レクチャー(現地自由参加)
11月8日(土)9:30-/10:30-
神経発達症の診かた
内川英紀(東千葉メディカルセンター小児科)
近年医療機関を受診する神経発達症の子どもが増加しており、児童精神科医だけでなく小児神経科医をはじめ一般小児科医にも対応が求められています。セミナーでは神経発達症の中で注意欠如多動症と自閉スペクトラム症について概説します。特徴について理解を深めるとともに、専門的な診療体制がなくても可能な心理社会的対応についての提示や、薬物療法など、診療で役立つ内容をお話ししたいと思います。
小児神経症候の診かた
青天目 信(国立病院機構大阪医療センター小児科)
神経の所見はこれから勉強する人にとっては、膨大な量があって勉強が大変なものの一つだと思います。画像をとればなんとかなるというのは間違いです。問診から得られた情報で考えたことを、診察により検証して、患者さんの身体の中で何が起きているのかを考えることは、とても興味深いものです。神経診察の基本をお伝えします。
◆ ◆ ◆