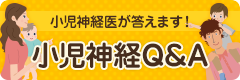第54回小児神経学セミナーイントロダクション
イントロダクション (講師敬称略、講演順)
随時更新して参りますのでお楽しみに!
副腎白質ジストロフィー(ALD)診療ガイドラインと新生児マススクリーニング
下澤 伸行(岐阜大学高等研究院)
小児大脳型ALDでは発症早期の造血幹細胞移植が唯一の治療法であるため、早期診断が極めて重要になる。一方で近年の移植技術の進歩により、従来の移植適応より進行した症例に対しても移植後に比較的、予後が改善された症例も経験されている。本講演では現在、改訂中の移植適応を含めた診療ガイドラインについて解説する。またさらなる予後改善から発症予防も視野にしたALD新生児マススクリーニングの国内外の取り組みについても紹介する。
ゲノム編集を用いた筋ジストロフィー治療法開発に向けて
堀田 秋津(京都大学iPS細胞研究所臨床応用研究部門)
Duchenne型筋ジストロフィーなどの難病の多くは、遺伝子変異が原因で筋萎縮が先天的に進行するため、根治を目指すには遺伝子変異の修復が鍵となる。我々はこれまで、患者由来iPS細胞を活用して、CRISPR-Cas9やCas3を用いた遺伝子修復方法を開発してきた。さらに、CRISPR-Cas9を生体内に送達する方法についても検討を重ね、ウイルス様粒子NanoMEDICや脂質ナノ粒子を用いた送達方法などを開発してきた。こうした技術開発状況について話題提供させて頂きたい。
てんかん診療の最前線:診断から治療まで
吉田 健司(京都大学医学部附属病院小児科)
小児のてんかん診療を取り巻く環境は目覚ましく変化しています。診断においては、国際抗てんかん連盟が2022年に発表したてんかん症候群分類により、従来の多くの病名が変更され、再定義されました。治療に関しても、原因遺伝子特異的な治療法やニューロモデュレーション治療などの選択肢が増えつつあります。本講義では、発作時脳波などを交えながら最新のてんかん分類を体系的に学び、後半では小児てんかんの内科治療および外科治療の最新の話題についても言及します。
小児における精神障害~うつを中心に~
堀内 史枝(愛媛大学大学院医学系研究科児童精神医学講座)
本邦の子ども人口は減少しているにもかかわらず、子どもの精神科を受診する子どもたちは増加の一途を辿っています。不登校の急増・児童生徒の自殺・市販薬の乱用など子どもを取り巻く環境は混沌としており、児童精神科医だけでは対応できない現状があります。本講演では、小児神経学の専門の先生方に共有させて頂きたい小児精神疾患について概説させて頂きたいと思います。
小児のリハビリテーションにおける小児神経科医の役割 ~脳性麻痺を中心に~
北井 征宏(ボバース記念病院小児神経科)
障害をもつお子さんの現実的な目標を家族、多職種と共有し、適切な介入について共に考えるプロセスの土台となる、脳性麻痺の包括的診断(病態、タイプ、機能レベル)について、頭部MRI、症例動画、周産期歴を提示しながら解説する。また、内服薬だけでなくボツリヌス治療やITB療法など小児神経科医が積極的に関わるべき治療介入について、「歩けますか?」「食べられますか?」などよく尋ねられる質問に対する考え方についても解説する。
脊髄髄膜瘤のフロンティア領域と小児神経科医に必要な日々の臨床
埜中 正博(関西医科大学脳神経外科)
本邦では神経組織が露出した状態で生まれてくる開放型の脊髄髄膜瘤、および病変部が皮膚により閉鎖された状態で生まれてくる潜在性二分脊椎(脊髄脂肪腫など)の双方を合わせ、年間1000出生に1名前後の患者が生まれていると推測される。特に脊髄髄膜瘤は脊髄の異常に伴う下肢の運動機能障害、排尿排便機能障害にとどまらず、その多くに発達遅滞を引き起こす水頭症や呼吸や嚥下障害を来す原因となるキアリⅡ型奇形を合併し、生涯にわたる医療ケアを要する。日本においては指定難病112番に指定される難病である。脊髄髄膜瘤患者の病態、発症原因、移行期医療の問題点、そして最新の治療法研究成果について報告する。
ランチョンセミナー
小児の神経生理学
石山 昭彦(東京都立神経病院神経小児科)
小児神経疾患の診療を行うなかで神経伝導検査、針筋電図検査ってできたらいいな、って思ってますよね。自己免疫性疾患や炎症性疾患などでは神経生理学的検査が診断の決め手!となることもあり得ます。今回のレクチャーは講義ですので、「できるようになります」とまでは言えませんが、その検査所見をどう解釈するの?という点について、検査所見の意味するところを深掘りしたいと思ってます。
セミナー初日のランチョンセミナーで講義1発目なので、なるべく疲れないよう、症例提示を織り交ぜてクイズの答え合わせをする感覚でお話をすすめていきます。今回の講義を聞いて、自信をもって検査所見を解釈ができるようになっていってください。
モーニングセミナー
小児神経各分野におけるこの数年の進歩
城所 博之(名古屋大学小児科)
このモーニングセミナーでは、過去1~2年の小児神経学分野における注目のトピックスを取り上げ、教育委員の熊田聡子先生、内川英紀先生、小島華林先生、そして私の4名がオムニバス形式で講演を行います。ぜひ、ご期待ください。
Group discussion
G1− 代謝疾患症例検討
成田 綾(医誠会国際総合病院小児科)
「勉強についていけなくなった」と外来で相談を受けて、神経代謝疾患を真っ先に疑うのはシマウマ診断である。しかしながら、疾患特異的な治療が次々と開発されている時代において、馬とニュータイプ(治療可能な)シマウマを同時に探すことに異論はないのではないだろうか。本グループディスカッションでは「勉強についていけなくなった」症例を通して、ニュータイプシマウマの尻尾の捕まえ方を一緒に考えてみたい。
G2− 脳波判断判断ソフトの使用方法
伊藤 祐史、白木杏奈、柳澤彩乃(名古屋大学医学部附属病院小児科)
新生児脳波を判読することで、ベッドサイドにおいて脳障害の有無やその程度を、リアルタイムかつ非侵襲的に評価することができる。本グループディスカッションでは、新生児脳波の講義を受けた後に、実際の脳波データを受講者のPC(Windowsに対応)を使用してグループごとに判読し、講師やチューターからフィードバックを受ける。新生児脳波の判読に慣れ親しんでいただき、今後の診療にご活用いただくことが目的である。
G3− 倫理
岡崎 伸(大阪市立総合医療センター小児神経内科)
小児神経の臨床現場において、倫理的なジレンマを感じることは少なくはない。今回は倫理および小児緩和ケアについて概要を説明した後、モデル症例を元にスモールグループでの議論と全体シェアを行い、倫理的な検討をともに学ぶ場にしたい。
倫理的なジレンマの例
■リスクが高い高度先進医療の施行について
■保険適応のない薬や治療法の施行について
■病状が進行した例・最重度の障害がある年長例への侵襲ある医療行為
G4− 小児のてんかん発作症候学
本田 涼子(国立病院機構長崎医療センター小児科)
てんかん発作の症候学は、てんかん焦点や異常なネットワークの推定の際に重要な情報を与えてくれます。てんかん診療における「基本の”き”」であり、患者さんやご家族による描写の聞き取りや、発作の様子を撮影したビデオなどを用いることで、日常診療の中で最も簡単に行うことができる診断技術です。ただし小児の発作症状は年齢によって変化し、低年齢では非常に単純で原始的なものであり脳の成熟に伴ってより複雑になるという特徴があります。また言語での表出が難しいため、発作の前兆に関する情報や意識レベルを確実に評価することも難しく、成人での症候学をそのまま当てはめることが難しい場合も多いです。さらにこの小児期の特徴として、焦点起始でありながら全般性の症状(たとえばてんかん性スパズムなど)として表れる場合や、逆に局在診断を誤らせるような焦点性の徴候を示すこともあります。このグループディスカッションでは、実際の発作のビデオや脳波、画像などを提示しながら、小児の発作症候から局在診断およびてんかん原性領域/ネットワークを一緒に考えていきたいと思います。
Clinical Conference
里 龍晴(長崎大学病院小児科)
特別レクチャー(現地自由参加)
11月2日(土)9:30-/10:30-
新生児マススクリーニング
丸山 慎介(鹿児島大学小児科)
神経難病に対する治療法の開発により早期診断・早期治療が極めて重要になってきています。そのような背景からいくつかの疾患に対する新生児マススクリーニングが始まっています。
その中でもホットトピックスである脊髄性筋萎縮症を中心に、小児神経科医が知っておくべき新生児マススクリーニングの現状とこれからについてお伝えしたいと思います。
小児の神経症候学
青天目 信(大阪大学小児科)
神経の所見をとるのは難しいですよね。検査や画像診断で何とかなると思ってしまう気持ちもわかります。でも、自分で診察をして何が起きているのかを考えるのは、とてもおもしろいものです。私も初心者の頃は、ジストニアを麻痺ですと学会報告をしたこともありました。基本から少しずつ学んで、診察を繰り返せば、何とかなります。神経診察の基本をお伝えします。
◆ ◆ ◆